|
八幡の弓名人(八幡) |  |
|
村の衆は土下座して謝った。 「この不届き者め。武士に向かって乞食扱いするとは、なお許せぬ。」 お侍は、より激しい怒りに身を震わせて、腰の刀を今にも抜き払おうとしたときや、甚平が、 「ま、ま待って下され、うっかりわしがしゃべってしもうたんですのや。なにとぞ、ご勘弁をご勘弁を。」 前に進み出て許しを請いました。 「無礼なことを言ったのはお前か。それほどの口をたたくからには腕に自信があろう。お前がこの弓を引いてみよ。」 弓なんぞ引いたことのない甚平にこういうではないか。 「こ、このわしに弓を…。」 「そうじゃ。お前が弓を引くのじゃ。もし的に当たれば、命だけは助けてやる。的を外せば命をもらうぞ。よいか。」 「そんな無茶なこと。殺生ですわ。」 「無茶も殺生もあるか。弓矢を持たぬか。」 無理矢理、甚平に弓と一本の矢を持たせたそうな。甚平はおどおどしながら村の衆に、 「えらいことになってしもうたわい。どうしよう。」 今にも泣きそうな顔でぼやいた。 「もうこうなってしもうたんや、甚平はん、やってみるしか助かる道はあらへんのや。なあ、思い切ってやれや。」 心の中は不安だらけだったが、甚平を励ましたそうや。 甚平の腕を見ようと少し離れていたお侍は、 「何をしゃべっているのだ。早く弓を引かんか。」 イライラしてどなるし、甚平は「我が命この一矢にあり」と覚悟を決めなあかんようになってしまった。 「は、はい、ただ今から。」 | |
|
震えながら弓引き場所に立ち、前方の的を見ると、まあなんと的の遠いこと。甚平は弓の弦をキリリッと絞って、心の中で「守護八幡氏神様」と一心に唱えて、矢を放ったそうな。 するとどうじゃ。矢は見事に的の真中に突き刺したではないか。固ずをのんで見ていた人々から大きな歓声、拍手。無理もない、どっとわき上がったそうや。が、甚平はきょとん。お侍は、 「みごとに射止めたぞ。だがな、今のは怪我の功名かも知れん。もう一矢放つのじゃ。」 |  |
|
家来にもう一本の矢を持って来させてまた甚平に渡した。ほっとしたのも束の間、またもやえらいことになった。村の衆もこんどはあかん、甚平の命もはやこれまで、と思い込んだ。 村の衆が見守る中で甚平は再び覚悟を決め、弓に矢を当てて、弦をグッと引き絞りました。的をにらんで、 「守護八幡氏神様。」 大声で祈った瞬間、不思議なことに矢は弓から離れてしまい、的の真中にブスッ。再び命中じゃ。固ずをのんで見守っていた村の若い衆や見物人たちの間からまたまたドッとどよめきがわき上がったのも無理のないことや。 「やったやった甚平。やったぞ甚平。」 村の若い衆は小躍りして喜び、甚平の方は、ただあ然とその場に立ち尽くしているだけだったそうや。 「まことにみごとな腕じゃ。お見それいたした。八幡氏神を唱えたが、そちの村の氏神は弓矢八幡であるのか。」 「へい、わしゃ伊賀国は名張郷の八幡村の甚平と申す百姓でござります。お侍さまのおっしゃる通り氏神さまは八幡社でござります。ですから村も八幡といっております。」 「やはり弓矢八幡の出か。道理でみごとな弓の腕だわい。約束通り命は助けてつかわす。京のみやげにわしの愛用のこの弓をつかわそうぞ。」 甚平は的に命中させた弓と矢を贈られたんじゃ。 村の若い衆たちが村に帰ってから、この出来事を年寄りに話し、それ以来、甚平の持ち帰った弓と矢は、八幡神社の本殿に供えられた。京都で矢を射た日が一月十七日だったので、その翌年から毎年その日に八幡神社の境内で弓を射る行事が行われるようになりましたんや。 「弓引き神事」といわれましてな。十人衆が「鬼」と墨で大きく書かれた的に向けて、矢を射ます。「鬼」は「悪鬼邪霊」。それを弓矢で退治して、村内の安全を祈願するわけですわ。もっとも最近では、甚平さんみたいに命中させることは少なくなって、的に近寄って引くことが多く、十二本当たれば終るようになってますんや。甚平さんは草葉のかげでどんな顔をしていることやら……。 話 畑中岩造さん(明治四十二年生まれ)ら十人 | |
| ●八幡神社2008/3/17現在。携帯で撮影。 | |
 ①八幡神社/参道入り口の石碑。八幡正八幡宮。昭和四十四年造営 | |
 ②八幡神社/石碑から数十メートル歩くと階段があります | |
 ③八幡神社/階段の下から。鳥居が見えます |
 ④八幡神社/階段を上るとさらに階段が |
 ⑤八幡神社/清めの水と二の鳥居。参道は左に曲がります | |
 ⑥八幡神社/二の鳥居をくぐると三の鳥居が見えます | |
 ⑦八幡神社/三の鳥居と拝殿 | |
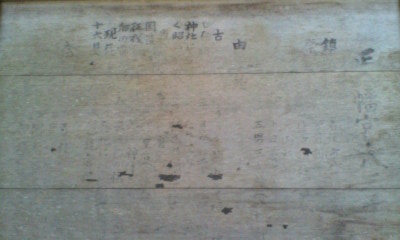 ⑧八幡神社/由緒?残念ながら、かすれて読めません。 | |
 ⑨八幡神社/拝殿。遠景 | |
 ⑩八幡神社/拝殿。額。正八幡宮八王子 | |
| ●八幡神撰田2008/4/26現在。携帯で撮影。 | |
① | |
② |
back